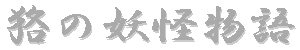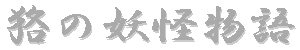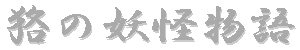
第弐回 変化の章
原題:物の怪になりたかった娘の話
作:名無し狢
わしは、ある夏に成り立ての日、とある山の頂の岩に俯せて、いい気分で
山々を見とった。
下界じゃ人間共が相も変わらず戦やらなんやら阿呆なこと繰り返しとった
が、そんなもんわしには関係ない。
物の怪になって、随分経つが、その間に色々な処にも棲んだが、この山々
ほど気に入った場所はなかったな。
獣たちはこのわしを恐れ敬ってくれるし、阿呆共は滅多に山に入って来ん
し、まぁあの世にそんなもんはないんやけど、この世の天国やったね。
そう。わしは物の怪。名前はないが、その名も知れ渡った狢や。
後世の阿呆が分福茶釜とか、飲み屋の前に変な焼き物の像を置いたり、狢
は狸の別称なりとか抜かすやつとかおって、現代ではすっかり違う印象を
持たれとるが、当時はまだ人を襲い人を喰らう恐れられた存在やった。
元は普通の生き物としての狢やったんやが、何時の頃かな、他の獣にも避
けられ、同族の狢や狐狸の類からも体良く敬われるだけの物の怪になっと
った。
この物語はそんなわしのちょっとした思い出話や。
物の怪としてのわしに付き合うのは同じ物の怪の灰色狐くらいやったかの。
奴がどこに棲んどるかは知らんが、時々酒を持ってきて、わしの処で他愛
ない話をしていく。
奴が酔うと愚痴や。奴は人間から神様扱いされとるが、人間と関わり合い
になるのを嫌っとる。まぁ、人間なんてどうでもええと思うとるんやろう。
奴の敵は狼や。何で狼を嫌うか、わしには理解できんが、奴の生き甲斐は
狼を襲い、虐めることや。もっとも狼に勝ったという話は聞いたことがな
い。狼にかるくあしらわれているらしい。そしてわしに愚痴る。
狼は同じ犬の仲間やのに、狢や狐狸を喰らう。そういう意味では狼はわし
の敵でもあるが、あの人間にも似た家族愛は嫌いやない。
そして、灰色狐の愚痴を聞きながら、わしは今までわしに関わってきた人
間共のことを思い出したりする。
「そう言えば、灰色狐とも長いこと会うてへんな」
わしは岩の上に俯せ、背中を陽に焼かれながら考える。あいつのせいやろ
うなぁ。
あいつがわしに関わりだして、もうどれくらいになるか。
そう、最初に会うたんは、もう秋も深まったころやった。
わしはいつものとおり、大狢に化けて、郷に出て幼女を拐って来た帰りや。
森抜けて、ある小川に差し掛かったところにあいつ、その娘がおったんや。
魚でも捕ろうとしとったんやろうなぁ、わしの姿みると、目ん玉丸くした
まま、腰抜かして小川にへばり込んでしもうた。
十六七くらいやったかなぁ、喰うて喰えんことはないが、人間は十にもな
らんくらいが美味いし、その日は獲物があったんでな、わしは特に気にす
ることもなく、通り過ぎたんや。その日はな。
後で思い返すと、その日も娘は郷のもんに比べて見窄らしい出で立ちやっ
たなぁ。それで、その後、すっかり忘れとったんやけどな。
それから幾日も経たんある日、わしは行商人に化けて郷に降りていったん
や。それが、その娘を見た二回目やったな。
ちょっと異様やったね。餓鬼共が村の外れの畦道でなんかしよるなと思う
たら、なんと小石を娘に投げつけとる。娘は怒りもせんと、当てられるま
ま俯いてこっちに来る。
娘がわしの横を通り過ぎる時に、わしはやっとあの娘やと気付いたんや。
郷には酒とかそんなもんを仕入れに行ったんやけどな、わしに酒を売って
くれる百姓の話では、その娘の一族は、所謂平家谷のもんらしい。
わしが物の怪になってそう経ってないころ、壇ノ浦っちゅうところで平氏
と源氏の最後の決戦が行われて、平氏は決戦に敗れて幼帝まで入水して、
平氏は滅んでしもうた。滅んだっちゅうても生き残りは居るわけで、そい
つらの多くがわしの棲むこの島に落ちてきて、人里離れて隠れ住むように
なった。それが、平家落人の隠れ里とか平家谷とか言われる集落や。
娘の一族が棲むんも、そんな集落の一つや。
当時の郷のもんはもともと平氏の息がかかっとったし、なんせ、可哀相な
境遇やから、匿っとったんやな。
それから時が流れて戦国の世になって、簡単に言うとこの郷を支配しとっ
た守護が追い出されて、平氏系のもんが乗っ取った。娘の一族は違ったが、
他の隠れ里のもんで、侍に戻ってこの平氏系の某に加担するもんも出た。
ところが、この平氏系某もあっさり攻め滅ぼされて、新しい領主は徹底的
に平氏系落人を弾圧し始めた。
娘の一族の存在が知れると郷にも害が及ぶ。とうとう疫病神扱いや。
娘やその一族がどうなろうとわしには関係なかったが、気にならんことは
ない。わしはその平家谷があると思しきところに行ってみた。
集落どころやない。たった二軒や。しかも二軒ともいまにも崩れそうなあ
ばら屋や。そして、その周りにほんのちょっとだけの畑。
山陰に早い日暮れで、辺りはすぐに暗くなる。わしはそのうちの一軒に近
づいた。
人の気配がする。隙間から覗くと、娘と賦せている年寄りの二人。明かり
も点けず、囲炉裏に火もくべず、娘は年寄りの足をさすっとる。年寄りは
なんやらぶつぶつ念仏みたいなのを唱えとる。
もう一軒はもぬけの空や。
わしは畑の方に進んだ。蕎麦畑らしい。秋の収穫後の萎びた茎が散らばっ
とる。そして、畑の切れるあたりに真新しい土まんじゅう。
おそらく、もぬけの空の方の主やったんやろうなぁ。
よく見ると、森の奥に古びた土まんじゅうが沢山ある。
ここも昔はもっと人が居って、畑も広かったんやろう。それが一人死に、
二人死んで土まんじゅうが増え、畑が狭まり森に呑まれていったんやな。
あの様子じゃ、じぃさんも長いことなかろう。わしは棲処に戻った。
そして、冬が来て、山は雪に閉ざされた。
わしの棲処は洞穴と木立を利用したもんで、雪風などは入り込まない。ま
た、火を焚くことで、中は快適や。
やが、冬の間も食料の調達は必要や。やから、雪がやんだ時など出かける。
そして、つい、あの集落に足が向く。
あばら屋は一軒になっておった。空き家の方は薪にでもしたか。やが、あ
ばら屋の周りの雪が払われているのを見て、わしは安心する。
そんなことが何回かあって、ようやく冬が過ぎた。
そんなある日、わしはとある頂に登り、そう、今日のように岩の上から山々
を見ておった。その時背後でざわめきがあった。
ここいらの獣はわしには近づかん。迷った氈鹿かなんかやろう。ひとつ、
脅かしてやるかと思い、わしは大狢に化けて、怒鳴った。
「誰じゃ、そこに居るのは。わしの邪魔すると、ぶち殺すぞ」
てっきり逃げると思うたら、そいつは近づいてきた。振り向いて驚いた。
あの娘やないか。
「人間の分限で何しに来た。さっさと去ね」
わしは娘を見据えて言った。娘はがたがたと震えながらも答える。
「な、名のある物の怪様と、お、お見受けい、いたします。どうか、わ、
私を、も、物の怪にして下さい。お、お願い致します」
わしは呆気にとられた。今まで命乞いをする人間とか、退治するとか豪語
して反対にわしにやられた人間はいたが、物の怪になりたいとは初めてだ。
「一族の、お、掟で、子細は申し上げられませんが、わ、私達の一族は、
他者との交わりを避け、一族のみで暮らしてきました。そ、その一族も
皆死に絶え、わ、私独りとなりました。この先、人として生きれない以
上、い、いっそ」
「いっそ物の怪にでもなって、無念を晴らすか」
娘は顔を上げ、わしを見る。
「め、滅相もございません。ただ、わ、私は人を超えたものとなり、い、
一族の想いを少しでも長く残したいと・・・」
わしは体中から妖気を迸らせ、娘に怒鳴る。
「ふざけるな。そんな下らんもののために、わしを煩わす気か」
娘はへたり込み、小水を漏らす。わしは娘にそっぽを向く。
「悪いことは言わん。人に生まれた以上、人として生きよ」
娘は長いことへたり込んだままだったが、やがてとぼとぼと戻って行った。
それで諦めたと思うとったが、それからも三日を空けず、娘はやってくる。
そして、今日も。わしはいつものように大狢に化け、音のする方に背を向
ける。背後に下草を掻き分けて娘が出てくる気配を感じる。
「狢様」
いつのころからか、娘はわしを狢様と呼ぶようになっていた。
「狢様、いよいよ、人として生きていけなくなりました。昨夜、私達一族
の存在を許さない者共が、私の里に火を放ちました。僅かばかりの建物、
畑、全て燃えました。身一つで逃げるのが精一杯でした」
ちらと娘を見る。襤褸同然の単衣を纏い、煤だらけになっている。
「あの者共は私が生きているのを許さないでしょう。狢様。物の怪に成れ
ないのであれば、せめて狢様に仕えさせて下さい。お願いします」
「断る。わしは悪しき物や。生き物、まして人間とは暮らせん」
娘は声を押し殺して泣く。涙がぼたぼたと地に落ちる。
「では、狢様が物の怪となった訳を教えて頂けないでしょうか」
「そがいな昔のことは忘れた。気が付いたら、人を襲い、人を喰らう物の
怪になっとった。それだけや」
娘は涙を流しながらお辞儀をして、戻っていった。
「せっかくのええ気分が台無しや」
わしは元の狢に戻り、森の中を抜け、あの集落へ行ってみた。なるほど、
焼け野原に変わっている。侍も何人か見える。山狩りでもする気か。
わしは棲処に戻りがてら、要所要所に術を施し、結界を張った。獣も人間
も術に惑わされ、結界の中に入ることは出来ん。
棲処に戻るころはもう暗くなっておった。棲処の入口は木々。わしが苗木
から育て、意のままに動くようになったやつらや。やが、木々の心はわし
にはわからん。獣と草木は分かり合えん。
まぁ、入口のこいつらは、わしには逆らわん。それでええ。
その木々の端の方、岩と接するあたりを見てわしは驚いた。
木と木の間にちょうどいい窪みが出来、そこにあの娘が寝ている。気持ち
よさそうに寝息すら立てとる。
おそらく娘はここがわしの棲処とは気付いておらんのやろう。そして、娘
をここに引き込んだのは、木々か。
「おまえら、この娘を守る気か?」
木々は、素知らぬふりで葉をそよそよと揺らす。
それからが大変や。わしは娘がおらんときを見計らってこそこそと外出せ
なならんようになった。
娘はそんなこととは露知らず、獣を捕ることを覚え、その肉を喰らうよう
になった。結界を解いた秋頃には随分と逞しくなっていた。
そんなある日、わしはまたとある頂で大狢になっていた。娘がやってくる。
娘がにこやかに、獣を喰らうことができるようになったと報告する。獣の
血を啜り、肝を囓り、肉を喰らっておれば、物の怪になれると思うてか。
わしは一喝した。
「そがいなことしたって、物の怪にはなれん。獣を喰らう獣になれたんな
ら、それでええ。獣として生きればええ」
わしの本心や。娘は無念と落胆の表情で戻っていった。その後、娘は例の
木々の塒で物思いに耽ることが多くなった。わしは外出しにくくなった。
また、冬が来て山が閉ざされた。木々は窪みを深くし、いつもなら裸にな
るくせに、娘の塒の処だけは葉を残して娘を白い魔物から守っている。
ある雪のやんだ日、娘の出かける気配がした。わしは後をつけようと出入
口の前に立ったが、木々は動こうとせん。
「こら、開けんかい。ただ見るだけや。どうこうする気はないわい」
木々は渋々と出口を作った。
娘が漕いだ雪の跡をわしは白兎に化けて追った。ずいぶん走って、人間が
よく通る峠道あたりで、ようやく娘を見つけた。わしは離れたところから
娘の所業を見た。
娘は雪の中から何かを掘り出し、手刀を当てる。凍っているのだろう。何
度も手刀を当てて、ようやく黒い石のようなものを取り出す。
暫く思い詰めたように石を眺めていた娘だが、徐に石に噛みつき、囓り取
る。石の残りが口から離れる。
娘は肩を落とし、ため息をつく。その刹那、石を落とし、手を口に当て、
ふさぎ込む。吐瀉の音がわしのところまで届く。
「行き倒れの人の肝を喰らおうとしたか。人を喰えば物の怪になれると」
無駄なことだ。娘は涙、涎、血糊の顔で再び石に齧り付く。わしはため息
をついて、棲処に戻った。
娘は日に日に痩せ細り、目だけが異様に光る。無理もない。喰う以上に吐
けば、そりゃ痩せる。冬が過ぎ、下界の雪が解ける頃には娘は戦場跡を廻
り、侍の屍肉まで漁るようになったようだ。相変わらず全て吐き出してし
まうようだ。木々に守られて寝ている時だけ安らかな顔を見せる。
そんなある日、酒を仕入れに行った百姓屋で、大胡某が化け物退治に乗り
出すという話を聞いた。どうやら、わしの存在と屍肉を漁る娘のことがごっ
ちゃになって、噂話が広がったようだ。
わしはまた結界を張った。大胡某が入り込まないように。そして、娘が外
に出ないように。
無駄やった。娘は相変わらず出かけている。
草木は個にして全、全にして個。棲処の木々に同調した木々の仕業か。娘
の為に、わしの術に背き道を造ってやっているのか。余計なことを。
時折戻り、木々に守られ安らかに眠る娘を窺うのがわしの習慣となった。
そして、ある日、木々のざわめきでわしは目が覚めた。
狼狽、恐怖、悲哀。獣達とは異なる思念がわしの頭に流れ込む。
「五月蝿い。いっぺんに喚くな」
わしは怒鳴り、大狢に化けて走り出す。娘の残した微かな匂いを追って。
結界の辺りで奇妙な穴を見つける。木々が拗くれ、根が絡み、行く手を塞
いでいる。穴はそれを避けるように何度も掘り直して向こうに続く。
いくつかの尾根を越え、谷を越え、河原に出たところで娘を見つけた。
河原には侍の屍が二十体はあろうか、その先に甲冑侍。これが大胡か。そ
して、更にその向こう、四つん這いになり大胡に対峙する娘。いや、左腕
が無くなっている。ぎらつく目も一つしか見えない。躰のあちらこちらか
ら鮮血がほとばしっている。
「ば、化け物め」
大胡が呻く。娘が吼え返す。そして娘の跳躍。大胡の刀が煌めき、娘の脚
が飛ぶ。娘の残った腕が大胡の眼前を払い、大胡の両目の辺りから血と目
の漿が噴き出す。
大胡が刀を放り投げ、絶叫をあげ顔を押さえる。娘は地に落ちると、再度
大胡に飛びかかり、その首筋に齧り付く。
一瞬の出来事だった。
わしが駆け寄った時には娘は倒れた大胡の腹を裂き、血の池に顔を突っ込
んでいた。
娘は大胡の肝を囓り取り、大胡の横に仰向けに倒れ込む。娘の喉が咀嚼の
動きを見せる。
娘はようやく弱いため息をつき、片眼をうっすら開ける。
「・・・むじな・・・さま・・・」
娘が微笑む。木々に守られ、寝ている時のように安らかに微笑む。
「・・・わ・・・わたし・・・やっと・・・」
うぐぇげっっ。娘は躰を曲げ横向きになり、茶色い肝と黄色い液体をはき
出す。そのまま暫くはひくついていたが、やがて静かになった。
わしは半分ほどになった娘の亡骸を抱きかかえ、棲処に戻り、娘を埋めた。
「一緒に生きてやればよかったかのう」
木々に訊いたが答はなかった。自分にも訊いたが答はなかった。
その夜、灰色狐が来て、黙って呑んだ。灰色狐がぽつんと言った。
「木が泣いてる」
完
初出:17MAY2007-01JUN2007 狢屋敷@タイトルネット
第壱回 転生の章に還る
第参回 は、まだあらへんでぇ〜
ぽんぽこもどる
狢 屋 敷に逝く さぁ、妖かしの世界へ逝こうか
前世物語に逝く 心が健全なもんはやめとった方がええ
2007 (c) Copyleft MUJINA